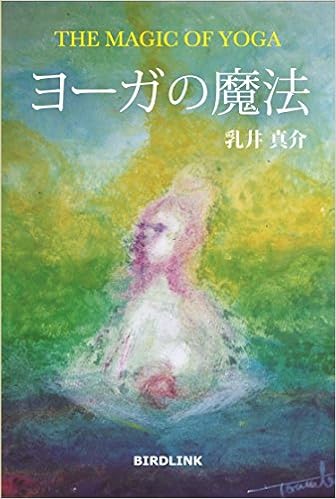死を見つめる練習
こんにちは。ディレクターの乳井真介(にゅういしんすけ)です。
今回は、「死」をテーマに少しお話したいと思います。
世界中で蔓延する新型コロナウイルスによって亡くなった方々の報道を毎日のように耳にすることで、「死」の存在を否が応でも意識せざるをえなくなった方も多いかもしれません。普通に生きていると、「死」は自分とは無縁のものと勘違いしてしまいがちですが、誰の人生にもいつの日か必ず死はやってきます。前回のブログでも言及しましたが、日本では毎年140万人が亡くなっており、これは一日に換算すると3500人、毎月10万人強の方が亡くなっている計算になります。このブログを書いている時点で日本の新型コロナウイルスによる死者数は100人程度ですが、たとえ新型コロナウイルスがなくても、毎年その14000倍もの方たちが亡くなっているのです。私たち誰もが人生の最後に迎えるネガティブイベントであるかのように思えるこの「死」をいかに深く見つめ、どう解釈するか。今回の新型コロナウイルスの蔓延はある意味その絶好の機会なのです。
10代後半の頃から、私は「死」について深く見つめる日々を送ってきました。自分がなぜこの世に生まれ、なぜ生き、なぜ死んでいくのか?この問いに対する答えを模索し続けていたのです。大学では哲学を専攻し、来る日も来る日も大学の図書館に通い、膨大な書物の中からどこかにその答えが書いてある本はないか、探し続けました。さまざま有名人や哲学者が書いた人生論や哲学書を読み漁りましたが、それでも大学の在学中には答えを見つけることはできません。やはり、どこにも答えはないのだろうか。そんな絶望感にかられ、最後の望みを託して、23歳の時に初めて渡ったインドでヨガに出会いました。正直なところ、ヨガ哲学には脳天を金づちで打たれるような大きな衝撃を受けました。大学の図書館をどれだけ探しても見つからなかった、自分の求めていた「人生の意味」に対する答えがすべて凝縮されていたからです。
ヒマラヤの奥地に住むヨガの聖者たちと出会い、私が最も感心したのは、彼らが死を全く恐れていないように見えたことです。まるで死が、衣服を着替え、食事をすることと何ら変わらない、日常の延長にあるかのように、彼らは一切心を乱すことなく、平常心で死と向きあっていました。その理由が知りたくて、何度となく渡印を繰り返しながら、ヨガの哲学の深奥に足を踏みいれていく中で、なぜ彼らが死を恐れないのか、その理由がわかるようになったのです。ゲームをする時、そのルールが分からなければゲームは心から楽しめませんし、敵が現れれば恐怖心がやってきて、パニックになることでしょう。しかし、ゲームのルールをよく理解していれば、敵の出現や主人公の死を恐れる必要はなくなり、ゲームを心から楽しめるようになります。今、多くの人が死を恐れているのは、人生というゲームのルールをよく理解していないことが原因なのです。
私がインドの聖者たちから学んだヨガ哲学の教えに関しては、私の著書の中で詳しく解説していますので、よろしければぜひ手に取って読んでみてください。
私が死に対する恐怖心を払拭できるようになったもう一つ大きな理由があります。それは私自身が繰り返し臨死体験をしているというものです。私は学生時代から趣味でブラジリアン柔術を続けていますが、相手の締め技が決まったあともギブアップすることなく耐え続けると、脳への酸素の供給がストップし、意識を失います。これを「落ちる」といいます。落ちる前は頸動脈を圧迫されることによる独特の苦しさがあるのですが、落ちる瞬間は身体全体の力がふっと抜けて、目の前の世界は白一色になりフェードアウトしていきます。この時、それまでの苦しみはうそのように消え、深い瞑想状態に入るような静けさが広がるのです。柔術ではここで相手が技をゆるめるので、しばらくすれば意識が戻りますが、もし技をかけられ続ければ、そのまま死を迎えることになります。長年ブラジリアン柔術を続ける中で、「落ちる」経験を繰り返すことで、私はこれまで死を何度も疑似体験してきました。若いころから深く死を見つめ続け、死を達観したヒマラヤに住むヨガの師たちと出会い、死は苦しみの極致ではなく、深い瞑想状態と同じであるということを身をもって体験していること。これが私自身が死に対する恐怖心を払拭できた理由だと思っています。
ヨガの根本経典には人がなぜ生まれ、なぜ生き、なぜ死ぬのか。そして死後、人はどこにくのか。これらすべてに関する教えが凝縮されています。私たち誰もがいつか経験しなければいけない人生最大のネガティブイベントであるように思える死を、どのようにしたらポジティブにとらえ直すことができるのか。ネガティブの極みである死をポジティブにとらえ直すことができた時、人生には他に怖いものがなくなります。心を乱す対象が一切なくなるのです。普段、深く考えて行っている方は少ないかもしれませんが、アーサナ(ポーズ)の練習の最後に、必ずシャヴァアーサナ(「死体」のポーズ)をとるのも、私たちが死の疑似体験をし、深く見つめ直すための練習の一環です。
ヨガの根本経典の一つである『バガバッド・ギーター』にはこんな一説があります。
「人が古い衣服を捨て、新しい衣服を着るように、主体は古い肉体を捨て、他の新しい身体に行く」
『バガバッド・ギーター』2.22
私たち人間の肉体は宇宙のエネルギーが生み出した波のようなものである。今形を持っている波がやがて海と融合し、新しい波として生まれ変わるように、肉体も常に変化し、やがて灰となり、あるいは土となって、宇宙エネルギーに帰っていく。人間にもたらされる生と死は広大な宇宙が生み出す自然現象であり、肉体的な死は魂のレベルでは新しい生の始まりである。これがヨガ哲学の根底にある死生観です。
同じ服を毎日着続ければ、汚れたり、穴が開いたり、ほつれたりして、ボロボロになっていきます。そんなボロボロになった服はさっさと脱ぎ捨てて、新しい服に着替えることでしょう。服と同じように私たちの肉体も、この世でさまざまな経験を積むうちに、シミやしわ、白髪が増え、ボロボロになっていきます。ボロボロになるまで肉体を使い続け年老いていくと、肉体を交換する時期がやってきて、私たちは死を迎える。そして、お肌はぴちぴち、髪もつやつやの赤ちゃんに生まれ変わり、新品の肉体を手に入れることができる。そう考えれば、死は必ずしもネガティブなものではなくなるのかもしれません。志村けんさんの死を多くの人が嘆いていますが、その間にも、もう志村けんさんはどこかで赤ちゃんに生まれ変わり、茶目っ気たっぷりに多くの人を笑わせているのだとしたらどうでしょうか?
こんな話をすると、なぜ死んだこともないのにそんな話を信じられるのかというツッコミを入れたくなる方がいるかもしれません。死んだらそこですべてが終わりになってしまうかもしれないじゃないか、と。確かに死後の事は誰にもわかりません。しかし、双子の子供をよく見ていると、まったく同じ遺伝子を持っていて、まったく同じ環境で育っているはずなのに、性格は真逆であるということがよくあります。これは「サンスカーラ」と言って、前世の潜在記憶が残っているからであるとヨガでは考えます。幼くして芸術や音楽などの分野で天才的な能力を発揮することができる天才児たちも、この前世の「サンスカーラ」が他人よりも強く残っていることで説明ができます。
インドではヨガの聖者が亡くなると、マハーサマーディ(大いなる至福の境地)に入ったとして祝う習慣があります。これは、この世で経験を積み続けることで、この世に対する執着を落とし、一切心残りなく死んでいくことができれば、その人は宇宙エネルギーと一体化し、至福の境地に至る。死は私たちが宇宙エネルギーと融合するために必要な通過儀礼であるという考え方によるものです。「仏になる」という言葉は、人が死ぬと「ほどけて」この世の背後にある宇宙のエネルギーとつながっていくという考え方から生まれました。実は日本人は古来このように非常にヨガ的な死生観を宿していたのです。葬式は、新たな人生への門出を祝う厳かな卒業式のようなものであるとしたらどうでしょう?もう20年近く前になりますが、「千の風になって」という歌が流行ったのをご存じの方も多いと思います。心の奥のどこかに誰もがヨガの死生観に通ずる考え方を持っているからこそ、この歌が多くの人の心に響き、流行ったのではないでしょうか。生まれ変わって新しい肉体を手に入れるにしろ、宇宙エネルギーと融合するにしろ、死を深く見つめ続けていくと、私たちが思っているほど死はネガティブな事態ではないことがだんだんと見えてくることでしょう。これがヨガの賢者たちが死を嘆かない理由なのです。
最後になりますが、ヨガとは別に、地球全体の一部としての人間存在という観点から見た人の死の意味を考えてみましょう。20世紀後半から爆発的に増大した人口によって、現在の地球はすでに危機的な状況に瀕しています。人類によってもたらされた急激な地球の温暖化と環境破壊によって、すでに地球上の50%以上の種が絶滅してしまいました。このまま人口が増え続け、このペースで人類がエネルギーを使い、環境を破壊し続けたら、温暖化は加速し、ここ100年以内にすべての生き物が住めなくなる死の惑星へと化してしまうことでしょう。地球全体の調和を保つという巨視的な観点で考えれば、いま私たちが大騒ぎしている人間の死と人口の減少は、大変皮肉なことに人間以外のすべての生物にとっては喜ばしい事態なのです。もしこの世から人間がいなくなれば、地球はすみやかに美しい緑と澄んだ水を取り戻し、再び多くの生命の喜びに満ちた美しい惑星へと生まれ変わることでしょう。
これまでさんざん地球から搾取し、環境を破壊し続けてきた人類に対する地球からのメッセージが、今回の新型コロナウイルスの蔓延であり、昨今騒がれている異常気象による台風や干ばつ、洪水や山火事などの被害であるように私には思えてなりません。最上部だけが醜く肥大した生存競争のピラミッドはやがて崩れ落ちます。自業自得という言葉の表す通り、わたしたち人類は、これまで自らのエゴが蒔いたカルマの種子を刈り取るらなければいけません。多くの生き物や植物、地球環境に対して、さんざん好き放題をして、搾取し続けてきたカルマの結果が、現在起こっている新型コロナウイルスの感染拡大であり、私たち人間の死だとしたら、私たち人類は自らの死を甘んじて受け入れる必要があるのかもしれません。多くの種を絶滅させておいて、自分たちだけは生き残りたいという発想は非常に身勝手だからです。このように、地球全体の一部としての人間の死を考えると、事態は非常に複雑になります。
人類の身勝手さがこの地球にいかに危機的な状況を作り出したのかを詳しく理解するために、下記の本を読んでみることをお勧めします。
ここまでさまざまな観点から、死を見つめる方法についてお伝えしてきました。今回のコロナウイルスに限らず、9.11の時も、東日本大震災の時も同じですが、生命を脅かされるような大きな危機に瀕したとき、人はそれまでの自分自身の行動のあり方を根本から見つめ直し、誤りを認め、大きく成長していきます。今回の騒動は、地球という惑星の上に住む私たち人類一人一人が自分自身の生と死の意味を一から見つめ直すことで、より健康で、より地球にやさしくなり、人類として一段上のステージに上がるためのステップなのかもしれません。まだ遅すぎることはありません。今この瞬間から、私たちの生き方が問われています。
乳井真介