ヨーガの基礎知識
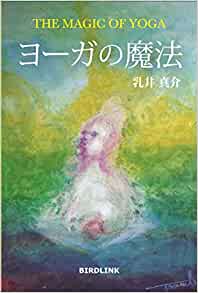
ヨーガは単なるポーズではなく、人生を輝かせる魔法だった・・・。ヤマ・ニヤマ、柔軟な身体を手に入れるための3つのカギ、チャクラ、瞑想、サマーディ・・・。インドとアメリカを十数年に渡り行き来し、これまでに1,000名以上のヨガインストラクターを輩出してきた著者が、これまでティーチャートレーニングの受講生だけに伝授してきた古代インドの究極の技法。本書ではその原理を一つ一つ明らかにしていきます。読めばヨガが分かるようになる。そして、“人生の意味”が分かるようになる。そんな一冊です。
本ヨーガの基礎知識では、本書籍より一部を抜粋してお届けします。
ヨーガの歴史
B. C. 3000年インダス文明(おぼろげな起源)
B. C. 1500年アーリヤ人のインド侵入
ヴェーダ文化の誕生(自然神崇拝)
B. C. 800年ウパニシャッド聖典群の誕生(ヨーガの原点)
B. C. 500年頃仏陀誕生
B. C. 400〜300年サーンキヤ学派(ヨーガの理論的ベース)
B. C. 200年〜A. D. 400年『ヨーガ・スートラ』、『バガバッド・ギーター』成立(ヨーガの二大経典)
A. D. 600年 タントラの隆興(ハタ・ヨーガの原点)
A. D. 1000年ハタ・ヨーガが体系化
A. D. 1600年『ハタ・ヨーガ・プラディピカー』成立(ハタ・ヨーガの根本経典)
A. D. 1900年代インド国外へ広がる

ヨーガとは何か?
ヨーガという言葉から皆さんは何を連想するでしょうか? 多くの方がさまざまなポーズを行うエクササイズや美容目的のストレッチ、あるいはアクロバットのようなものをイメー ジしたのではないでしょうか? そして、ヨーガは身体が柔らかい人たちが行うものであり、柔軟な身体や健康を手に入れたい一部の人のためのものであると思い込んではいないで しょうか? 実際にはヨーガが必要ない人はこの世に一人もいません。望むと望まざるとにかかわらず、私たちは皆何かしらの形ですでにヨーガを行っています。この世に生きとし生ける全ての存在がヨーガの実践者なのです。
“ヨーガ”という言葉はサンスクリット語で“結合”、“つながり”を意味します。語源は馬と馬車をつなぐ馬具“軛(くびき)”を指す“ユジュ”という言葉で、このユジュがヨー ガという言葉に変化する過程で、馬と馬車という相異なるもの同士を一つにし、「つなぐ」という意味を強くもつようになりました。よって、ヨーガという言葉自体にはポーズやエ クササイズ、ストレッチあるいはアクロバットという意味は含まれていません。相異なる二つのものを一つにつなげ、結合させていく作業、それがヨーガなのです。ですから、何かと何かをつなげ一つにしていくとき、私たちは無意識にヨーガを実践しています。

ここで少し日常生活において「つなぐ」、「つながる」とい う言葉を使うシチュエーションを思い浮かべてみましょう。「手をつなぐ」、「電話をつなぐ」、「(駅伝などで)タスキをつなぐ」、「友達の輪がつながる」……などちょっと考えるだけでも色々なシチュエーションが思い浮かぶはずです。たとえ ポーズを行わなくても、これらの何気ない日常のふとした瞬間にじつは私たちはヨーガを行っています。ヨーガは多くの人が考えるよりもずっと私たちの身近な場所で行われている のです。
そして、これらヨーガが行われている場所に共通して満ちているのは人生の豊かさです。試しに先ほどのシチュ エーションから「つながり」を取り去ってみましょう。「手を切る」、「電話がつながらない」、「タスキがつながらない」、「一 人ぼっち」……といった、想像するだけでどこか寂しくなってくる状況が生まれてしまいます。インターネットは1台1台別々のコンピューター同士が回線で「つながり」合ってできたシステムですが、このインターネットの登場によって世 界中の人々が急速に親密になり、私たちにインターネットがない時代に戻ることなど考えられないほどの豊かさをもたらしてくれたことはご存じのとおりです。
それがどのようなつながりであるのかにかかわらず、つながりが増えれば増えるほど私たちの人生は豊かさで満ちていくのです。私たち誰もが無意識のレベルではこの事実に気づいています。それゆえ、 私たちは「もっとつながりたい、もっとつながりたい」といつも心の中で「つながり」を求め続けるのです。
このように、ヨーガは単にポーズを行うことではありませ ん。身体が若返り、しなやかで健康になるのはもちろんですが、 それ以上に私たちの人生の在り方を根底から変化させ、美しい光に満ちた楽園へと導く魔法の力をヨーガは宿しています。 たとえポーズの実践を行っていなくても、豊かな人生を謳歌している人生の達人たちは、皆ヨーガの達人でもあります。 世の中にはヨーガの魔法を使いこなしていることに気づいていないヨーガの魔法使いたちがたくさんいるのです。
ヨーガの八支則
『ヨーガ・スートラ』は起源前後の時代、聖者パタンジャリによって編纂されたとされるヨーガの根本経典です。この『ヨーガ・スートラ』の第2 部門、「サーダナ・パーダ」はヨーガの具体的な実践方法について説かれた部門です。サーダナ・パーダでパタンジャリはさまざまな対象にチューニングを行い、「つながり」を手に入れるために必要な具体的なアプローチを8つに段階分けして紹介していきます。この8つのアプローチは一般に「ヨーガの八支則」と呼ばれます。「ヨーガの八支則」はヨーガの実践を正しく深めていく上で必要不可欠な大変重要な考え方です。真剣にヨーガを実践したい方は忘れずに覚えておきたいものです。「ヨーガの八支則」は以下の8 つのステップよりなります。
- ヤマ(禁戒)
- ニヤマ(勧戒)
- アーサナ(ポーズ)
- プラーナーヤーマ(調気法)
- プラティヤハーラ(感覚制御)
- ダーラナー(集中)
- ディヤーナ(瞑想状態)
- サマーディ(三昧)
ヤマ(禁戒)は日常生活で慎むべき5 つの戒律を守る段階です。ヤマの5つの戒律はアヒンサー(非暴力)、サティヤ(正直)、アスティヤ(不盗)、ブラフマチャリヤ(禁欲)、アパリグラハ(不貪)よりなります。
ニヤマ(勧戒)は日常生活で心がけるべき5 つの戒律を守る段階です。ニヤマの5つの戒律はシャウチャ(清浄)、サントーシャ(知足)、タパス(苦行)、スヴァディアーヤ(聖典の学習)、イーシュヴァラ・プラニダーナ(神への献身)です。パタンジャリは私たちにまずこれらヤマ、ニヤマの10 の戒律を通して日常生活を規律正しく整えることからヨーガの実践を始めることを推奨します。
アーサナはポーズの実践を通して身体を整える段階です。
プラーナーヤーマは呼吸を通して気の流れを整える段階です。
プラティヤハーラは心をより繊細にコントロールして感覚器官をコントロールする段階です。
第6段階のダーラナーから第8 段階のサマーディは心を一点に集中しチューニングを進めていく段階です。最終的にサマーディというこの上なく甘美な果実をなるべく長く手元に置き続けることができるようになること、それが「ヨーガの八支則」の目的です。
サマーディという果実は必ずしも「ヨーガの八支則」を実践しなければ手に入らないわけではありません。スーパーや八百屋で手軽に果実を手に入れることができるように、パチンコをすることでも、スポーツをすることでも、美味しいものを食べることでもインスタントな「三昧」を手に入れることは可能です。しかし果実を手に入れようとした時、店が閉まっていたり、売り切れになっていたりしたら欲しい果実が手に入らないのと同じように、外部からサマーディを手に入れようとする方法は不確かで不安定です。
パタンジャリが私たちに提案するのはこのような不確かで不安定なサマーディの手に入れ方ではありません。パタンジャリは私たちにサマーディという果実をたわわに実につける「ヨーガの木」の栽培方法を提示します。たわわに果実を実らせるためにはまず根が十分に広がっていないといけません。
ヤマ、ニヤマのそれぞれ5 つの戒律はヨーガ実践を深めるために必要な10 本の根です。根が広がると幹が太くなり枝が広がります。アーサナは私たちの身体を鍛え整えることで、ヨーガの木の幹を太くし、枝を広げるのに役立ちます。枝が広がれば多くの葉がつき、光合成をして多量のエネルギーを作り出すことができるようになります。プラーナーヤーマは身体全体に生命エネルギーを漲らせ拡張することを助ける、ヨーガの木の葉です。大量のエネルギーが満ちることで樹液の流れは円滑になり、より繊細なエネルギーのコントロールが可能になります。
プラティヤハーラでは心を繊細にコントロールしながら5 つの感覚器官を自由自在にコントロールしていくことを目指します。そして樹液の流れが円滑になった時、つぼみがつき、花が咲き始めます。ヨーガの木のつぼみは集中力です。ダーラナーで強まった集中力はディヤーナの段階で開花します。
集中力が開花すると瞑想状態が生まれます。そして、たくさんの瞑想の花が咲いた後に、この上なく甘美なヨーガの果実、「サマーディ」が実るのです。ヨーガの木を自分自身の手で大きく育てることができれば、私たちはもはやサマーディという果実を求めて彷徨う必要はなくなります。どこにいても好きな時に好きなだけサマーディという果実の甘美さに酔いしれることができるようになるのです。
世の中にはそれがヨーガの木であることを知らずに、自己流でヨーガの木を大きく育て上げ、サマーディの果実を手に入れてしまう人生の達人も少なからず存在します。しかし、私たちの多くはなかなかうまくヨーガの木を育て上げることができず、サマーディという果実を手に入れるためにもがいています。今から2000 年前、パタンジャリはサマーディの果実がたわわに実るヨーガの木の栽培に成功しました。そして、自身の見出したヨーガの木の栽培方法を後世に伝えていかねばならない。そんな慈愛に満ちた使命感から『ヨーガ・スートラ』を完成させました。
『ヨーガ・スートラ』に記されたヨーガの実践法を正しく深めていけば、やがて誰もがパタンジャリと同じようにサマーディという果実を存分に味わうことができるようになるのです。このようにして『ヨーガ・スートラ』に則りヨーガの実践を深めていくヨーガは「ラージャ・ヨーガ(王者のヨーガ)」と呼ばれます。
ヨーガの起源
ヨーガがいつどこで生まれたのか? じつのところよくわかっていません。もしヨーガが「つながり」を手に入れるた めの作業だとしたら、家族や仲間、自然との深い「つながり」 の中で生きているチンパンジーやオランウータンなどの自然界の動物たちも、ある意味ヨーガの実践者であるといえるかもしれません。考古学的に確証できる最古のヨーガの起源は紀元前3000年頃に栄えたとされるインダス文明の時代です。 インダス文明はインド土着の民族であるドラヴィダ人がインド北西部(現在は大半がパキスタン領)を流れる大河インダス川流域に築いたとされる古代文明の一つです。
19世紀になり、考古学者たちの手によって発掘されたインダス文明の遺跡から、ヨーガを実践しているとおぼしき人物の彫られたレリーフが多数発掘されており、このことからインダス文明の時代にはヨーガらしきことが行われていたのではないかと推測されています。推測と書いたのはインダス文明で使われていたインダス文字が解読不能であるため、レリーフが正確に何を表したものなのかは現在でもわかっていないためです。
ヨーガの原型がもう少し明確になるのが紀元前1700年以降の時代です。紀元前1700年から1500年頃、インダス川周辺にアーリヤ人たちがやってきたと推測されています。アーリヤ人はもともと南ロシアのコーカサス地方(現在のカザフスタン周辺)に住んでいたとされる民族ですが、紀元前 2000年頃から豊かな土地を求め移動を始めたと考えられています。移動を始めたアーリヤ人たちのうち、コーカサス地方から西へ移動した集団はのちにギリシャ文明を築き、現在のヨーロッパ人たちの祖先になりました。一方、南に移動した集団は中東に定住し、現在のイラン・イラク人たちの祖先 になりました。
さらに中東から東へ足を延ばしたアーリヤ人の集団がインダス川流域に到達したのです。高度な文化を有し体格的にも勝っていたアーリヤ人たちは、当時すでに衰退していたと推測されるインダス文明を築いたドラヴィダ人たちを自分たちの支配下に置きました。そして、ドラヴィダ人たちの文化を吸収しながらインド独自の文化を築いていったのです。こうして生まれたインド独自の文化を「ヴェーダ」 と呼びます。“ヴェーダ”は“智恵”という意味の言葉です。 このヴェーダで使用されたのがサンスクリット語です。サン スクリット語の発音には英語に近いものが多数ありますが、 それはこのような歴史的背景によるものです。ちなみに英語 で“つなぐ”という意味をもつ“yoke”という言葉がありますが、 “yoga”と発音がよく似ています。
今から5000年も前にインダス文明を築いたドラヴィダ人の文化と、のちにギリシャ文明などを築くことになるアーリヤ人の文化という、二つの高度な文化が奇跡的に融合して生まれたインド独自の文化ヴェーダ。このヴェーダとは一体どのような文化だったのでしょうか?
初期のヴェーダ文 化の特徴は「自然神崇拝」です。初期のヴェーダ文化では自然界に存在するありとあらゆる存在、太陽、雷、暴風雨、河 川、大地、火など……を神に見立て祭祀を行いました。祭祀は祭壇を設け、祭火を焚き、讃美歌を歌い、時に生贄をささげ、盛大に行われていたようです。そしてその祭祀によって雨乞いをするなど、自然現象が自分たちの望むように現れることを願ったのです。
初期のヴェーダで崇拝されていた自然神の中には雷の神インドラ(帝釈天)や天空の神ディヤウス(ゼ ウス)など日本の神道やギリシャ神話に取り入れられ、現在も崇拝されている神もいます。また、ヴェーダの祭祀で焚か れていた聖火は“ホーマ”と呼ばれますが、これが日本に伝 わって護摩供養の“護摩”になりました。紀元前1200年頃成立したとされる最古のヴェーダ文献である『リグ・ヴェーダ』 にはさまざまな自然神への讃歌が収められています。
このような自然神崇拝という信仰形態は、インドに限らず、 日本を含め世界中の文化でみられる原始的な信仰形態です。 文明が未発達な時代、農耕技術や建築技術、灌漑技術は現在と比べると非常に未熟でした。そのため、自然が少し猛威を振るえば、たちまち人間は生命の危機にさらされていたのです。この時代、自然は人間にとって圧倒的な崇高さと威厳を宿していました。文明をもたない人間が自然に対して取りうる唯一の選択肢は、自然を神に見立て、その神たちへの崇拝の儀 式を洗練させることだけだったのです。このヴェーダにおける自然神たちへの祭祀で中心的な役割を任っていたのが「バ ラモン」と呼ばれる神と交信する特殊な能力をもつとされる人たちでした。
以上、乳井真介著『ヨーガの魔法』より抜粋


